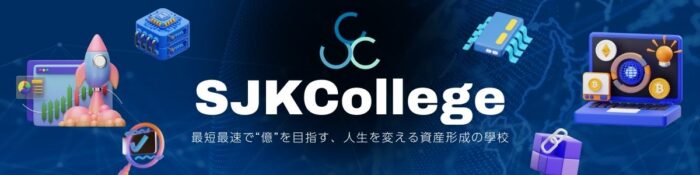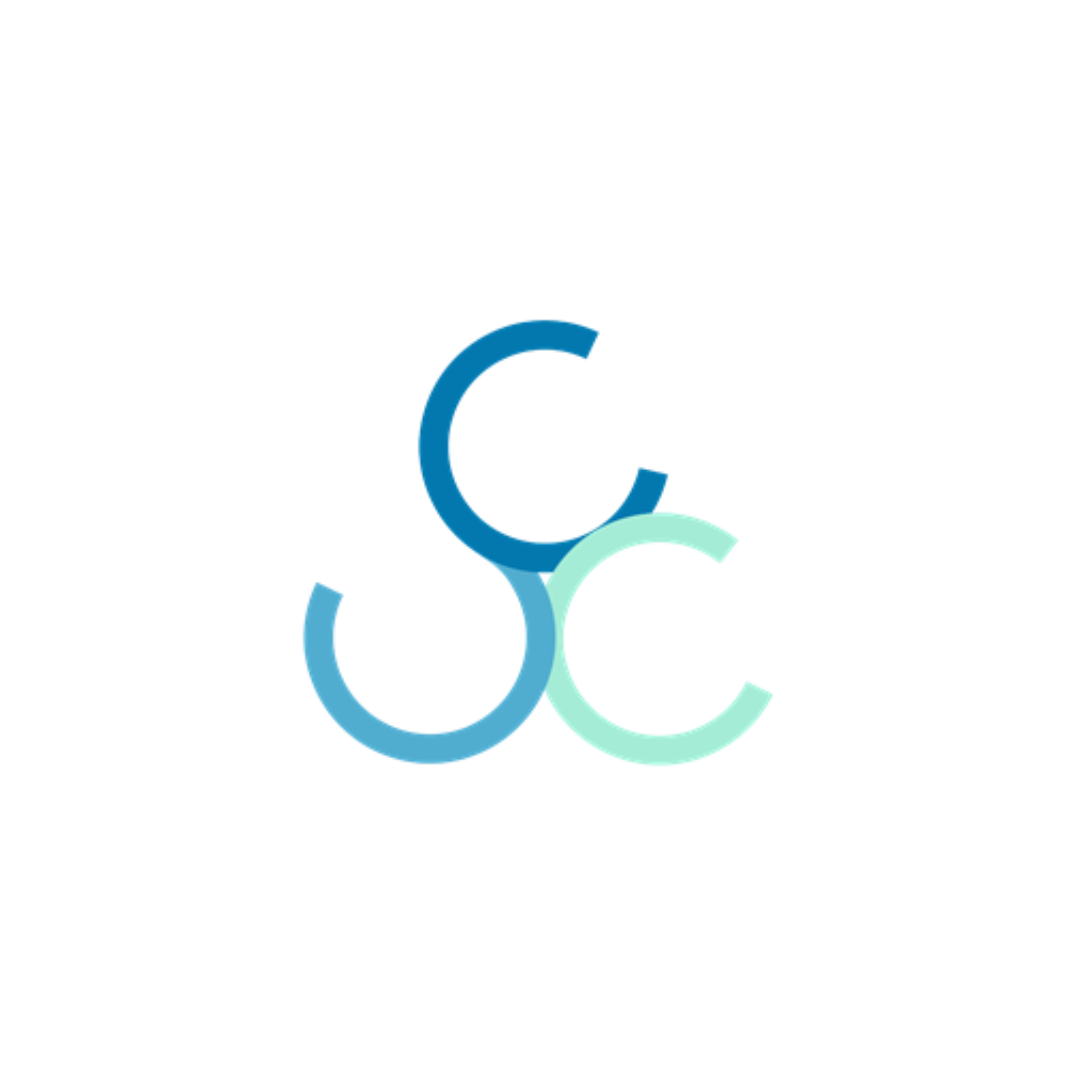生活防衛資金とは、急な出費や収入の減少に備えるためのお金です。
生活防衛資金を用意しておくと、事故やトラブルで急な出費が必要となったり、働けなくなり収入が少なくなってしまった場合に備えることができます。
生活防衛資金に対する正しい理解は、経済的自由を達成するためには絶対必要です。
この記事では、生活防衛資金に関する下記について解説します。
①いくら生活防衛資金を貯れば良いのか?
②生活防衛資金を貯めるべき3つの理由
③生活防衛資金に関するよくある疑問
生活防衛資金はいくら貯めたら良いのか?
必要な生活防衛資金は、働き方や家族構成、生活費などによって異なります。
重要なのは、生活防衛資金は収入ではなく「生活費」で考えることです。
例えば、年収が300万円であっても、年間の必要な生活防衛資金が必ずしも300万円とは限りません。
生活費を基準に考えるため、もし生活費が20万円であれば、年間で必要な生活防衛資金は240万円となります。
生活できる最低限のお金ってことだね!
ここでは、3つのケースで、必要な生活防衛資金の目安を解説していきます。
①会社員
②自営業者
③子育て世帯
①会社員の場合
会社員の場合、「生活費の半年分」を目安に生活防衛資金を貯めておくことをおすすめします。
会社員は安定的な収入があり、突然仕事がなくなる可能性も低いです。
さらに、会社が倒産したり、体調不良で働けなくなった場合でも、失業保険や傷病手当金などの公的保険によって最低限の収入が保障されます。
②自営業者の場合
自営業者の場合、「生活費の1~2年分」を目安に生活防衛資金を準備することをおすすめします。
自営業者は収入が不安定であり、会社員と比べて公的な保障も限られており、失業保険や傷病手当金も適用されません。
ですので、会社員よりも多めの金額を備えておくと安心です。
また、公的な保障の不足をカバーするために、就業不能保険を検討している人もいるかもしれません。
保険は、起こる確率は低いけど大きな損失をカバーするためのものであり、自営業者の場合は就業不能保険の検討をした方がいいかもしれません。
ただし、民間の就業不能保険は必要性が高い一方で、コストパフォーマンスの良い保険は少ないです。
最近では保障内容が改善されてきていますので、もし就業不能保険に加入を検討しているなら、下記の条件で選ぶことをおすすめします。
・障害認定の基準が公的制度と同じ。
・病気や障害で働けない間は、月額5~15万円の保険金が受給される。
・保険料が1,000~3,000円程度。
・精神疾患も多少はカバーしてくれる。
③子育て世帯の場合
子育て世帯の場合、「会社員であれば1年分、自営業者であれば2〜3年分」を目安に生活防衛資金を貯めておくことをおすすめします。
なお、子どもの教育資金は別途、貯蓄を基本に準備することをおすすめします。
学資保険を活用する方も多いかもしれませんが、SJKCollegeでは学資保険をおすすめしません。
✅手堅く貯めたいなら、元本保証されている預金で備えるべき。
→ 保険では元本割れや、不払いの可能性がある。
✅お金を増やしたいなら、自分で運用すべき。
→ 利回りが低く、手数料を保険会社に支払う必要はない。
将来確実に使用する教育資金のような資金を貯める場合、最優先すべきは元本の安全性です。
学資保険は、貯蓄と保険が組み合わさった商品であり、余計なリスクが発生する可能性があるため注意が必要です。
※学資保険については下記の記事を参考にされて下さい。
”https://sjk-g.com/home/6025″生活防衛資金を貯めるべき3つの理由
続いて、生活防衛資金を貯めるべき3つの理由を解説していきます。
「なぜ生活防衛資金が必要なのか?」を理解することで、貯蓄への意欲も高まるでしょう。
①精神安定剤になるから
②お金が貯まりやすい体質になるから
③投資で成功しやすくなるから
①精神安定剤になるから
理由1つ目は、「精神安定剤になるから」です。
生活防衛資金の有無による、精神的な影響を比較してみます。
✅ 生活防衛資金が貯まっている
・失業しても、ゆとりを持って次の就職先を探せる。
・体調を崩しても、治療費を支払える。
・大切な人が困っていても、助けられる。
✖ 生活防衛資金が貯まっていない
・生活費に困るから、会社を辞められない。
・焦って転職活動をして、上手くいかない。
生活防衛資金があることで余裕が生まれて、本当にやりたいことが選べるんだね!
②お金が貯まりやすい体質になるから
理由2つ目は、「お金が貯まりやすい体質になるから」です。
お金を貯めやすい体質とは、保険などの固定費を見直し、支出をコントロールできる状態を指します。
たとえば、生活防衛資金が蓄えられている場合、不必要な保険に加入する必要はありません。
✖ 医療保険
✖ 貯蓄型生命保険
✖ 変額保険
✖ 外貨建て保険
✖ 車両保険
✖ 学資保険
必要な民間保険は下記の3つだと考えます。
・掛け捨て生命保険
・火災保険
・自動車保険(対人・対物無制限)
貯蓄で支払える範囲の治療費や修理費にも、保険をかけている人は大勢います。
不必要な保険に加入することで、手元に残るお金が減ってしまうことになってしまいます。
また、生活防衛資金が貯まると、無駄な買い物を減らすことができます。
その理由は、欲しいものが買える状態になると、買わないという選択肢も持てるからです。
さらに、「買えるけど買わない」と「買えない」という状況には、精神的にも大きな差が存在します。
✅買えるけど買わない
→ストレスが溜まらない
✖買えない
→ストレスが溜まる
生活防衛資金があれば、買わない選択ができるのでストレスが溜まりません。
そのため、ストレスなく無駄な買い物を減らせ、よりお金が貯まりやすくなります。
お金を無理なく貯められるようになると、先ほど解説したように余裕が持てるようになります。
その結果、本当に必要なものかどうかを判断する能力が身につくのです。
そして、判断基準として重要なのは、価格ではなく「価値」で考えることです。
価格ではなく価値で判断し、余裕を持ってお金を貯めていこう!
③投資でも成功しやすくなるから
理由3つ目は、「投資でも成功しやすくなるから」です。
生活防衛資金が貯まっていると、株価の暴落などの時でも冷静に対応できるようになります。
投資を行っていると、いずれ必ず不景気や暴落に遭遇することがあります。
しかし、どれだけ心構えをしていても、生防衛資金が不足していると、不安に襲われて売却してしまう人が多くなります。
また、不景気になると株価が下がるだけでなく、下記のようなことも同時に起こります。
・給与や賞与のカット
・労働時間の削減や解雇
・仕事の激減(フリーランス)
ただし、株価の急落や不景気は永続するものではありません。
一時的に家計が赤字になったとしても、生活防衛資金があれば冷静に対処することができるでしょう。
生活防衛資金に関するよくある疑問
続いて、生活防衛資金に関するよくある疑問について解説していきます。
疑問①:生活防衛資金とローン返済はどちらを優先すべきかな?
疑問②:生活防衛資金が貯まるまで投資をしてはいけないのかな?
疑問③:いくらあれば保険を解約して良いのかな?
疑問④:どこに生活防衛資金を貯めるべきかな?
疑問①:生活防衛資金とローン返済はどちらを優先すべきかな?
生活防衛資金とローン返済の優先順位は、金利によります。
たとえば、住宅ローンなど金利が低い場合は、生活防衛資金を優先的に貯めることが適切です。
ただし、残りの返済額や現在の収入によっても状況は異なります。
一方、リボ払いやカードローン、消費者金融などの高金利な借金がある場合は、優先的に返済を進めることが重要です。
なお、一般的なリボ払いの金利は10〜15%程度です。
たとえば、100万円をリボ払いで毎月1万円ずつ返済していくと、手数料の合計は約60万円にも上ります。
無駄な手数料を取られないように、なるべく早く返済しよう!
疑問②:生活防衛資金が貯まるまで投資をしてはいけないのかな?
基本的には、生活防衛資金が貯まってから投資を始めた方が望ましいです。
なぜなら、生活防衛資金のない状態で投資を行うと、精神的な余裕が失われ、市場の暴落時にパニック売りしてしまう可能性があるためです。
ただし例外として、投資をしながらでも生活防衛資金を貯められるなら、投資を開始しても問題ありません。
資産を増やし自由な時間を得るためには、投資は不可欠であり、始めるのが早いほど資産形成に有利です。
もし、生活防衛資金を貯めながら投資をするのであれば、まず無駄な保険を解約することをおすすめします。
投資にお金を回す前に無駄な保険を解約し、固定費を削減する方が効率的です。
また、貯めることに精一杯で投資に十分な資金を回せない場合は、「時間に投資」することも検討してみてください。
お金や時間がないという方もいますが、飲み会や自分の趣味の時間などを削減することで、1日に1~2時間を確保することはできるはずです。
もちろん、何を優先するかは個人の価値観によって異なります。
ただし、経済的な自由を実現したいのであれば、時間やお金を自己投資や資産運用に割けるようにすることが大切です。
疑問③:いくらあれば保険を解約して良いのかな?
すでに必要な生活防衛資金が貯まっているなら、不要な保険は全て解約しましょう。
そもそも保険は、起こる確率は低いものの、生活が困るようなトラブルに備えて加入するものです。
繰り返しになりますが必要な保険は3つだけと考えます。
・掛け捨て生命保険
・火災保険
・自動車保険(対人・対物無制限)
ただし、貯金が10万円程しかなく、病気やケガに対する不安を抱えている人は、都道府県民共済の入院保障2型を検討することをおすすめします。
保険の見直しは、他人の言葉に流されて契約や解約をするのではなく、自分自身で判断することが重要です。
疑問④:どこに生活防衛資金を貯めるべきかな?
生活防衛資金は、緊急時にすぐに使えることが重要なので、銀行の普通預金に預けておくことをおすすめします。
たまに、銀行の倒産リスクを考慮して自宅の中にタンス預金する方もいますが、自宅での現金保管は盗難のリスクが高まるため、おすすめできません。
火災や盗難の発生確率は銀行の倒産よりも高いため、銀行に預ける方が安全です。
まとめ
この記事では、生活防衛資金をいくら貯めるべきか、貯めるべき理由について解説しました。
生活防衛資金の金額は人によって異なりますが、下記を目安にしてみてください。
・会社員:生活費の半年分
・自営業者:生活費の1~2年分
・子育て世帯:生活費の1~3年分
そして、貯めるべき理由は下記の3つです。
①精神安定剤になるから
②お金が貯まりやすい体質になるから
③投資で成功しやすくなるから
また、借金がある場合には金利が高い借金返済を優先し、同時に最低限の貯金もできるような状況を整えましょう。
そのためには、下記の6つの項目を重視した固定費の見直しを行いましょう。
①通信費
②光熱費
③保険
④家
⑤車
⑥税金
何の為に、資産形成をするのか、最終的なゴールは人によって異なります。
生活防衛資金を貯めることは、資産形成をしていく上で欠かせない目標の一つです。
SJKCollegeでは、日々「お金の勉強」について発信しています。
しっかりと学び、人生楽しむための資産形成をしていきましょう♪